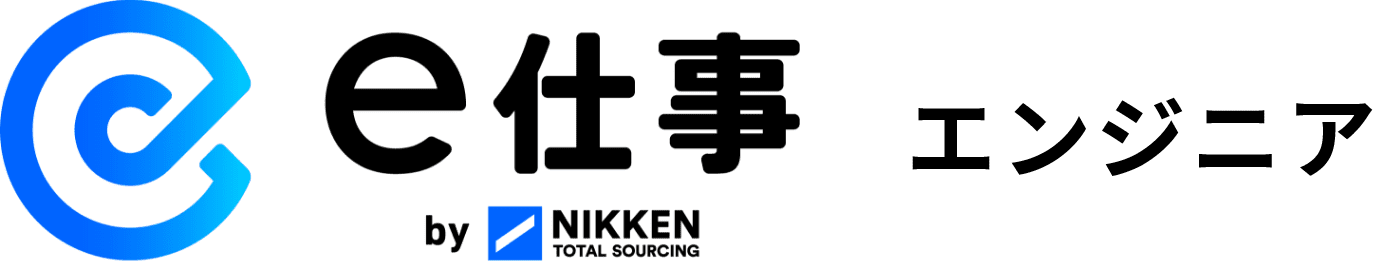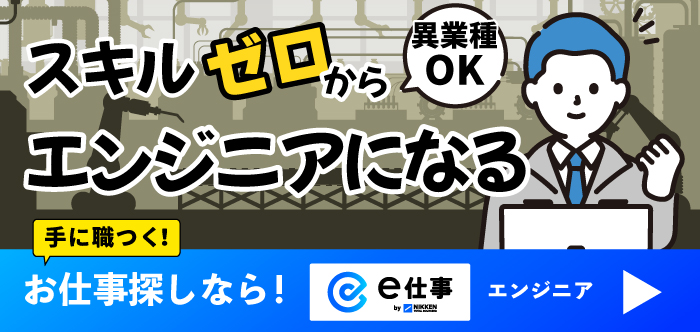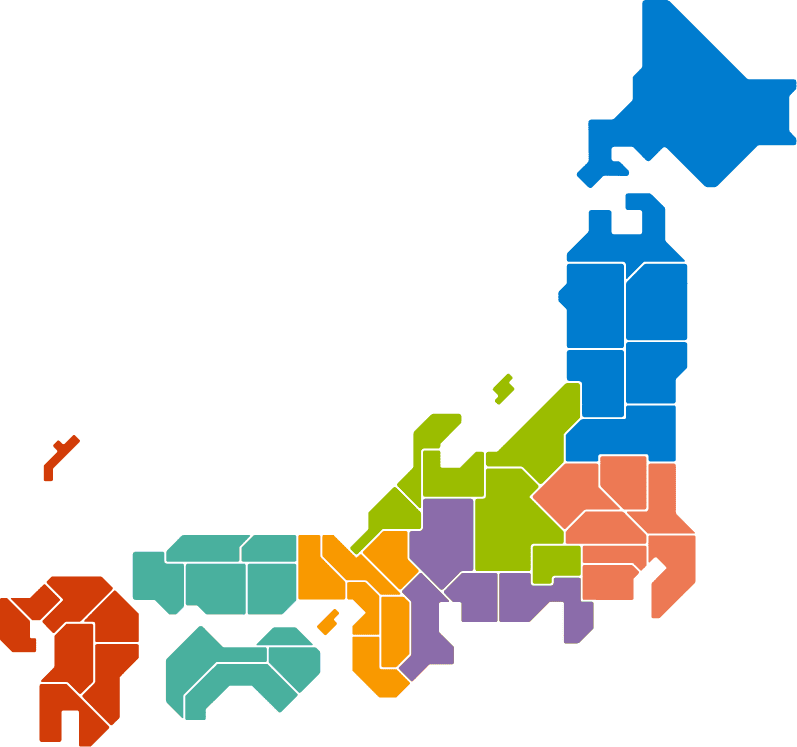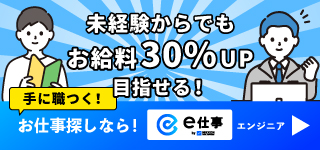工場での品質管理とは?主な業務や働くうえでの基礎知識などを詳しくご紹介
2025/08/05
製造業の求人を見ていると「品質管理」という職種をよく目にしませんか?なんとなく検査をする仕事というイメージはあっても、実際にどんな業務をしているのか詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
実は品質管理の仕事は、単に製品をチェックするだけではありません。工場で作られる製品の品質を守り、時には改善提案を行い、お客様に安心して使っていただける製品を届ける重要な役割を担っています。
本記事では、品質管理の具体的な業務内容から必要なスキル、キャリアパスまで、転職を考えている方に向けて詳しく解説していきます。未経験の方でも品質管理の仕事がイメージできるよう、現場のリアルな情報をお伝えしていきましょう。
そもそも品質管理って何をする仕事?現場のリアルな業務内容
品質管理の仕事を一言で表すなら「製品の品質を守る番人」といったところでしょうか。でも実際の業務はもっと幅広く、奥深いものです。
製造現場で日々行われている品質管理の仕事は、大きく分けて「工程管理」「品質検証」「品質改善」の3つに分類されます。それぞれがどんな仕事なのか、現場の様子を交えながら見ていきましょう。
製造ラインを見守る「工程管理」の実際
朝一番、品質管理担当者は製造ラインを巡回することから一日が始まります。工程管理とは、製品が正しく作られているかを日々チェックし、安定した品質を維持する仕事です。
例えば、作業員が決められた手順通りに作業しているか確認したり、設備が正常に動いているかチェックしたりします。特に重要なのが「作業の標準化」です。
誰が作業しても同じ品質の製品ができるよう、作業手順書を整備し、新人教育を行うのも品質管理の大切な役割。ベテラン作業員の「カン」や「コツ」に頼るのではなく、誰でも理解できるマニュアルを作成し、現場に浸透させていきます。
また、製造設備の定期点検スケジュールを管理し、故障による品質トラブルを未然に防ぐのも工程管理の一環です。機械の調子がおかしいと感じたら、すぐに保全部門と連携して対応します。
製品の良し悪しを判定する「品質検証」の現場
品質検証は、多くの人がイメージする「検査」の仕事です。しかし実際は、完成品だけでなく原材料から製造途中の製品まで、あらゆる段階でチェックを行います。
原材料が納入されたら、まず受入検査を実施。仕様書通りの品質かどうか、サンプリングして確認します。製造工程では、各工程ごとに中間検査を行い、不良品が次工程に流れないようにします。
そして最終的に完成品検査を経て、ようやく出荷可能となります。検査方法は製品によって様々で、目視検査から精密測定器を使った寸法測定、性能試験まで多岐にわたります。
食品工場なら細菌検査や官能検査(味・におい・見た目のチェック)、機械部品なら強度試験や耐久試験など、その製品に求められる品質基準をクリアしているか一つ一つ確認していくのです。
トラブル発生!原因を突き止める「品質改善」の仕事
どんなに注意していても、時には不良品が発生したり、お客様からクレームが入ったりすることがあります。そんな時こそ品質管理の腕の見せ所です。
まずは現場に急行し、何が起きているのか状況を把握。不良品のサンプルを集め、いつから、どの工程で、なぜ発生したのかを調査します。原因究明には「なぜなぜ分析」という手法をよく使います。
例えば「製品に傷がついた」という不良が発生したとします。なぜ傷がついたのか?→搬送中にぶつかったから。なぜぶつかったのか?→固定が甘かったから。なぜ固定が甘かったのか?→作業手順が明確でなかったから...というように、真の原因にたどり着くまで「なぜ」を繰り返します。
原因が判明したら、再発防止策を立案し、関係部署と協力して実行に移します。作業手順の見直し、設備の改良、検査体制の強化など、二度と同じ問題が起きないよう対策を講じるのです。
工場の種類で変わる品質管理の仕事内容
品質管理の基本的な考え方は同じでも、扱う製品によって具体的な業務内容は大きく異なります。ここでは代表的な4つの業界の品質管理の特徴を見ていきましょう。
食品工場なら「衛生管理」が最優先
食品工場の品質管理で最も重要なのは、なんといっても衛生管理です。消費者の口に入るものを扱うため、少しの油断が食中毒などの重大事故につながりかねません。
毎日の業務では、製造環境の清潔さをチェックすることから始まります。作業員の手洗いは適切か、作業着は清潔か、製造機器の洗浄・殺菌は確実に行われているか。これらを細かくチェックし、記録に残します。
製品の検査では、微生物検査が欠かせません。大腸菌群や一般生菌数を調べ、安全性を確認。また、アレルゲン検査も重要で、表示と異なるアレルギー物質が混入していないか厳しくチェックします。
多くの食品工場では、HACCPという国際的な衛生管理手法を導入しており、品質管理担当者はこの仕組みを理解し、運用していく必要があります。
自動車工場は「ミリ単位の精度」との勝負
自動車や自動車部品の品質管理では、非常に高い精度が求められます。わずかな寸法の違いが、走行中の異音や振動、最悪の場合は事故につながる可能性があるからです。
日々の検査では、三次元測定機やマイクロメーターなどの精密測定器を駆使して、部品の寸法を0.01ミリ単位で測定します。組み立て後は、実際に動作させて異音がないか、スムーズに動くかなど、五感を使った検査も重要です。
また、自動車業界では統計的手法を活用した品質管理が発達しています。工程能力指数(Cpk)を算出し、製造工程が安定しているか数値で管理。異常の兆候を早期に発見し、不良品の発生を未然に防ぎます。
国際規格であるIATF16949に準拠した品質マネジメントシステムの運用も、自動車業界の品質管理担当者に求められる重要な仕事です。
化学工場では「分析のプロ」として活躍
化学製品や素材を扱う工場では、品質管理担当者は「分析のプロフェッショナル」として活躍します。製品の成分が規格通りか、不純物は含まれていないか、化学分析によって確認するのです。
分析室では、液体クロマトグラフィーやガスクロマトグラフィーなどの高度な分析機器を操作し、製品の組成を詳細に調べます。また、引張試験機や硬度計を使って、材料の物理的特性も測定します。
化学物質を扱うため、安全面での配慮も欠かせません。有害物質の含有量が法規制値以下であることを確認し、SDSデータシートの作成にも関わります。
分析データの信頼性を保つため、分析機器の日常点検や校正、分析手順の標準化なども重要な業務。正確なデータを出すことが、製品の品質保証につながるのです。
医薬品工場は「命を守る最後の砦」
医薬品の品質管理は、文字通り人の命に関わる仕事です。わずかなミスが患者さんの健康被害につながる可能性があるため、他の業界以上に厳格な管理が求められます。
GMPという医薬品製造の国際基準に従い、原料の受入から製品の出荷まで、すべての工程で品質をチェック。有効成分の含量試験、溶出試験、無菌試験など、多岐にわたる試験を実施します。
特徴的なのは、すべての作業や試験結果を詳細に記録し、長期間保管すること。万が一問題が発生した際に、いつ、誰が、どのような作業を行ったかを追跡できるようにするためです。
また、製造環境の管理も重要で、クリーンルームの清浄度測定、作業員の衛生管理など、汚染防止に細心の注意を払います。
品質管理の仕事で身につく3つの必須スキル
品質管理の仕事を通じて身につくスキルは、その後のキャリアでも大いに役立ちます。ここでは特に重要な3つのスキルについて詳しく見ていきましょう。
データと向き合う「分析力」
品質管理の仕事では、日々大量のデータと向き合います。検査結果、不良率、工程能力指数など、様々な数値を収集・分析し、そこから意味のある情報を読み取る力が自然と身につきます。
例えば、ある製品の不良率が上昇傾向にあることに気づいたとします。単に「不良が増えた」で終わらせず、いつから増えたのか、特定の製造ラインで多いのか、原材料のロットと関係があるのかなど、データを多角的に分析します。
エクセルを使ったデータ集計やグラフ作成は日常茶飯事。ヒストグラムや管理図などの統計ツールを使いこなし、問題の本質を見抜く力が養われます。
この分析力は、品質管理以外の仕事でも重宝されるスキル。経営企画や営業企画など、データ分析が必要な職種への転職にも有利になります。
現場と経営をつなぐ「コミュニケーション力」
品質管理は一人で完結する仕事ではありません。製造現場、営業、時には経営層まで、様々な立場の人と協力しながら仕事を進める必要があります。
不良が発生した時、製造現場に改善を求めるのは簡単ではありません。「品質管理がうるさいことを言ってきた」と思われないよう、なぜ改善が必要なのか、改善することでどんなメリットがあるのかを分かりやすく説明する必要があります。
また、品質データを経営層に報告する際は、専門用語を使わず、経営判断に必要な情報を的確に伝える力が求められます。
このような経験を通じて、相手の立場に立って考え、分かりやすく伝えるコミュニケーション力が自然と身につくのです。
トラブルを未然に防ぐ「リスク管理力」
品質管理の究極の目標は、不良品を出さないこと。そのためには、問題が起きてから対処するのではなく、事前にリスクを察知し、予防する力が必要です。
新製品の立ち上げ時には、どんな不良が起きる可能性があるか、過去の経験やデータを基に予測します。FMEAという手法を使って、起こりうる不具合とその影響度を評価し、対策を講じます。
日々の巡回でも、「いつもと違う音がする」「作業員の動きがぎこちない」など、わずかな変化に気づく観察力が大切。大きなトラブルになる前に手を打つことで、被害を最小限に抑えます。
このリスク管理力は、プロジェクトマネージャーや経営企画など、リスクを考慮した判断が求められる職種でも活かせるスキルです。
未経験から品質管理職を目指すなら知っておきたいこと
品質管理の仕事に興味を持った方のために、転職前に知っておくと役立つ基礎知識をまとめました。これらを理解しておけば、面接でも一歩リードできるはずです。
PDCAサイクルは品質管理の「基本のキ」
品質管理の世界で最も有名な考え方が「PDCAサイクル」です。Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)の頭文字を取ったもので、この4つのステップを繰り返すことで継続的な改善を実現します。
例えば、不良率を下げるという目標があったとします。まず現状を分析し、改善計画を立てます(Plan)。次に計画に基づいて対策を実施(Do)。一定期間後に効果を検証し(Check)、うまくいった点は標準化し、うまくいかなかった点は再度改善します(Action)。
このサイクルを回し続けることで、品質は着実に向上していきます。PDCAは品質管理だけでなく、あらゆる仕事に応用できる普遍的な考え方。これを理解し、実践できることをアピールできれば、未経験でも評価されるでしょう。
QC七つ道具って何?現場で使える分析手法
品質管理の現場では「QC七つ道具」と呼ばれる分析手法がよく使われます。難しそうに聞こえますが、実は誰でも使える実践的なツールです。
代表的なものを挙げると、パレート図は不良の種類を多い順に並べたグラフで、どの不良から対策すべきか優先順位が一目で分かります。特性要因図(魚の骨のような図)は、問題の原因を体系的に整理するのに便利です。
管理図は、工程が安定しているかを判断するグラフ。データが管理限界線を超えたら、何か異常が起きているサインです。
これらのツールは、品質管理の教科書には必ず載っている基本中の基本。転職活動中に勉強しておけば、即戦力として期待されるかもしれません。
品質管理と品質保証、実は違う仕事だった
求人票を見ていると「品質管理」と「品質保証」という似たような職種名を見かけます。実はこの2つ、似ているようで役割が異なります。
品質管理(QC)は、主に製造現場での品質作り込みを担当します。日々の検査や工程管理、不良対策など、モノづくりの現場に密着した仕事です。
一方、品質保証(QA)は、もっと広い視点で品質を保証する仕事。製品企画の段階から関わり、お客様に届いた後のアフターフォローまで責任を持ちます。クレーム対応や監査対応なども品質保証の重要な業務です。
企業によって業務範囲は異なりますが、一般的に品質管理は現場寄り、品質保証は管理寄りの仕事といえるでしょう。自分がどちらに興味があるか、考えてみると良いかもしれません。
品質管理の仕事、ぶっちゃけ大変?やりがいは?
品質管理の仕事には、正直なところ大変な面もあります。でも、それ以上にやりがいも大きい仕事です。現場のリアルな声をお伝えしましょう。
「最後の砦」としての責任とプレッシャー
品質管理は、不良品がお客様に届くのを防ぐ最後の砦。この責任の重さは、時にプレッシャーとなります。
自分が見逃した不良品が市場に出てしまったら...そう考えると、検査の手が震えることもあるかもしれません。特に食品や医薬品など、人の健康に直接関わる製品を扱う場合、その責任はより重大です。
しかし、だからこそやりがいも大きいのです。自分の仕事が、お客様の安全・安心を守っている。企業の信頼を支えている。そう実感できた時の充実感は、他の仕事では味わえないものがあります。
品質問題を未然に防ぎ、「今月もクレームゼロだったね」と現場から感謝される。そんな瞬間が、品質管理担当者の誇りになるのです。
製造現場との板挟みになることも
品質管理の仕事で避けて通れないのが、製造現場との関係です。時には対立することもあります。
例えば、納期が迫っている時に品質基準を満たさない製品が見つかったとします。製造現場は「少しくらい基準を外れても大丈夫だろう」と出荷したがりますが、品質管理としては「ダメなものはダメ」と言わざるを得ません。
営業からは「お客様が待っているんだ」とプレッシャーをかけられ、製造現場からは「品質管理のせいで納期に遅れる」と責められる。まさに板挟み状態です。
でも、ここで妥協してしまっては品質管理の意味がありません。なぜ基準を守る必要があるのか、粘り強く説明し、理解を得る努力が必要です。最初は煙たがられても、品質問題を防いだ実績を積み重ねれば、次第に信頼関係が築けるようになります。
数字で見える成果がモチベーションに
品質管理の仕事の良いところは、成果が数字ではっきり見えることです。不良率が10%から5%に下がった、クレーム件数が半減した、工程能力指数が向上した...自分の努力が数値として表れます。
また、改善活動の効果もすぐに分かります。新しい検査方法を導入したら不良の流出がゼロになった、作業手順を見直したら作業時間が20%短縮できた、など、具体的な成果が見えるのです。
毎月の品質会議で改善事例を発表し、他部署から「すごいね」と評価される。品質向上に貢献したとして表彰される。そんな目に見える評価が、次へのモチベーションにつながります。
地道な仕事が多い品質管理ですが、確実に成果が出る、やればやった分だけ結果がついてくる仕事といえるでしょう。
品質管理職への転職を成功させるために
最後に、品質管理職への転職を考えている方に向けて、成功のためのポイントをお伝えします。
取っておくと有利な資格はこれ!
品質管理の仕事に必須の資格はありませんが、持っていると有利になる資格がいくつかあります。
最もポピュラーなのが「品質管理検定(QC検定)」です。4級から1級まであり、品質管理の基礎知識を体系的に学べます。未経験なら3級からチャレンジしてみると良いでしょう。
業界によっては、より専門的な資格が評価されることもあります。食品業界なら食品衛生管理者、化学業界なら危険物取扱者、といった具合です。
また、ISO9001の内部監査員資格も人気があります。多くの企業がISO9001を取得しているため、内部監査ができる人材は重宝されます。
ただし、資格はあくまでプラスアルファ。それよりも、なぜ品質管理の仕事をしたいのか、どんな貢献ができるのかを明確に語れることの方が重要です。
志望動機で差をつけるポイント
品質管理の志望動機を書く際のポイントは、「なぜ品質管理なのか」を明確にすることです。
単に「ものづくりに興味がある」では弱いです。品質管理ならではの魅力、例えば「製品の品質を通じて、企業の信頼を支える仕事がしたい」「データ分析を活かして、工程改善に貢献したい」など、具体的に書きましょう。
また、これまでの経験をどう活かせるかも重要です。営業経験があるなら「顧客視点を持って品質向上に取り組める」、事務経験があるなら「細かい数値管理や書類作成が得意」など、アピールポイントを見つけてください。
未経験でも、日常生活で品質にこだわった経験や、PDCAを回して改善した経験があれば、それを具体的に書くと良いでしょう。
将来性抜群!品質管理職が求められる理由
品質管理職の需要は、今後ますます高まると予想されています。その理由はいくつかあります。
まず、消費者の品質に対する意識の高まりです。SNSの普及により、品質問題はあっという間に拡散される時代。企業にとって品質管理の重要性は増すばかりです。
また、グローバル化により、国際基準に対応できる品質管理人材が求められています。海外工場の品質指導や、輸出製品の品質保証など、活躍の場は世界に広がっています。
さらに、IoTやAIなどの新技術を品質管理に活用する動きも活発化。従来の品質管理スキルに加え、新技術を使いこなせる人材は引く手あまたです。
製造業がある限り、品質管理の仕事はなくなりません。むしろ重要性は増していく一方。将来性という点では、非常に魅力的な職種といえるでしょう。
品質管理はモノづくりを支える誇れる仕事
品質管理の仕事は、決して派手ではありません。でも、私たちの生活を支える大切な仕事です。
スーパーで買った食品が安心して食べられるのも、車が安全に走れるのも、薬が効果を発揮するのも、すべて品質管理担当者の地道な努力があってこそ。
確かに責任は重く、時には現場との調整に苦労することもあります。でも、自分の仕事が製品の品質向上につながり、お客様の笑顔につながる。そんなやりがいを感じられる仕事です。
未経験から品質管理を目指すのは簡単ではないかもしれません。でも、真摯に品質と向き合う姿勢があれば、必ず道は開けます。PDCAサイクルを理解し、データ分析の基礎を学び、なぜ品質管理がしたいのかを明確にする。そんな準備をして、ぜひチャレンジしてみてください。
品質管理の世界で、あなたの新しいキャリアが花開くことを願っています。
手に職つくお仕事探しは求人サイト「e仕事エンジニア」がおすすめ!
手に職つくお仕事に興味がある人は求人サイト「e仕事エンジニア」がおすすめ!
例えば
- 大手メーカーで最先端の技術を身につけられる
- 資格取得をサポート
- 未経験でも安心の充実研修
など様々なメリットがあります。無料で利用できるのでぜひチェックしてみてくださいね。
e仕事エンジニアはこちらから↓↓↓
関連記事
求人カンタン検索
こだわりのメリットでカンタン検索。希望の条件をクリックして下さい。
都道府県で探す
業種で探す
こだわり条件で探す
- 待遇
- 働き方
- 募集条件
- 職場環境