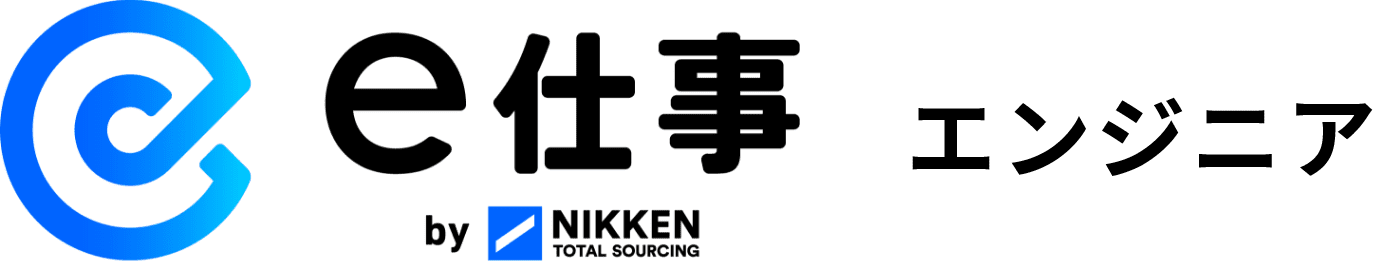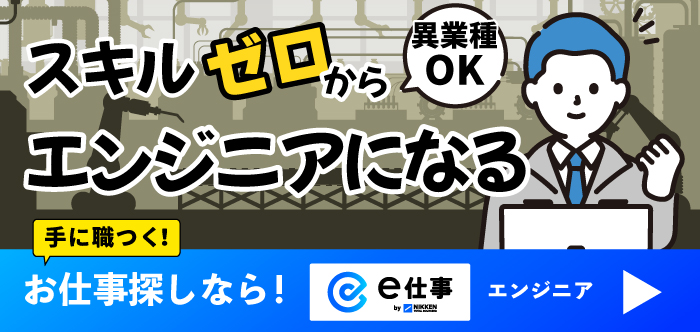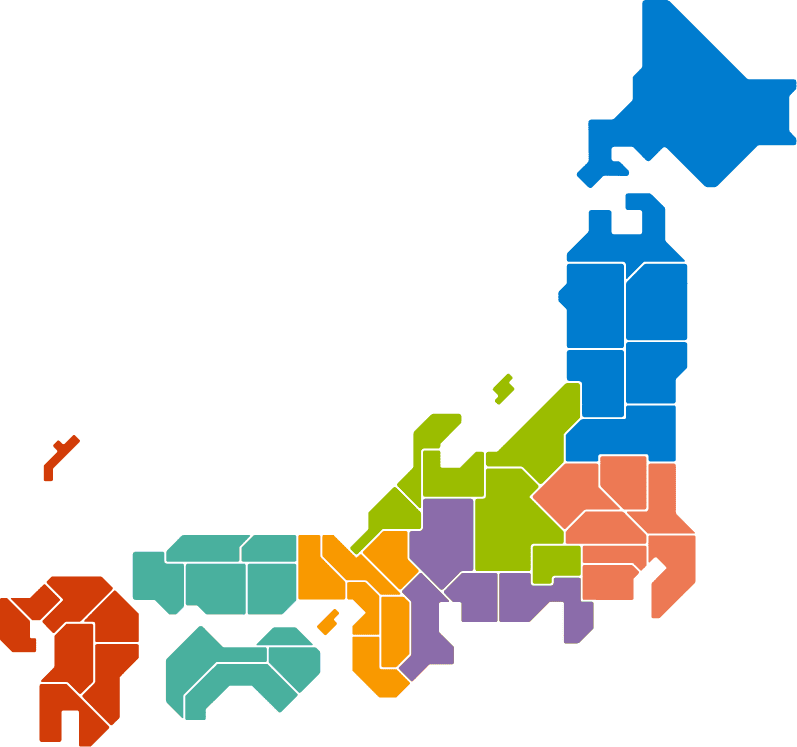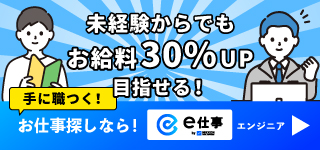製造現場の設備保全に役立つ認定資格「自主保全士」とはどんな仕事?具体的な業務内容や保全エンジニアとの違いについて解説
2025/10/15
日本の製造業において、設備の安定稼働は生産性と品質を左右する最重要課題です。その課題解決の鍵を握るのが、製造オペレーター自身が設備管理能力を身につけることを目的とした「自主保全士」という資格制度です。本記事では、製造現場で活躍する自主保全士の具体的な業務内容から必要なスキル、さらには保全エンジニアとの役割分担まで、詳しく解説していきます。
自主保全士は「設備に強いオペレーター」を認定する資格制度
自主保全士とは、製造オペレーターが日常的に行う設備保全活動の知識と技能を認定する資格制度です。従来の「生産は現場、保全は専門部署」という分業体制から脱却し、オペレーター自身が設備管理の主体となることで、トラブルの未然防止と生産効率の向上を実現する仕組みとして注目を集めています。
JIPMが認定する民間資格として年間1万人以上が受験
自主保全士は、公益社団法人日本プラントメンテナンス協会(JIPM)が2001年から運営している民間資格です。制度開始から20年あまりで累計13万人を超える認定者を輩出し、現在では延べ16万人以上の自主保全士が全国の製造現場で活躍しています。
年間受験者数は1万人を超え、その多くが自動車製造業や化学工業に従事する現場オペレーターです。450社を超える企業が導入しており、製造業界における実践的な資格として広く認知されています。
民間資格でありながら、その実用性と効果の高さから、多くの企業が社内教育プログラムに組み込んでいます。受験者層も幅広く、新入社員から中堅社員まで、それぞれのスキルレベルに応じた資格取得を目指しています。
製造現場で自ら設備保全を実践できる人材を育成
自主保全の基本理念は「自分の設備は自分で守る」という考え方にあります。これは、TPM(Total Productive Maintenance)活動の一環として位置づけられており、設備を日常的に使用するオペレーター自身が、点検や清掃、簡単な整備を行うことで、設備の異常を早期に発見し対処する仕組みです。
自主保全士資格は、この理念を実践できる人材を体系的に育成することを目的としています。JIPMでは、製造オペレーターに必要な能力を「4つの能力」と「5つの知識・技能」として体系化し、それらを身につけた人材を客観的に評価・認定しています。
資格取得を通じて、オペレーターは設備の構造や機能への理解を深め、異常の兆候を見逃さない観察眼を養います。また、単に知識を身につけるだけでなく、実際の現場で応用できる実践的なスキルの習得に重点が置かれています。
2級と1級で求められる役割とスキルレベルが異なる
自主保全士資格には2級と1級の2つの等級があり、それぞれに求められる役割と能力レベルが明確に定められています。
2級は、製造部門の一員として自分の担当設備について自主保全を実践できるレベルです。日常的な点検や清掃、給油、簡単な部品交換など、基本的な保全作業を確実に遂行できる能力が求められます。受験資格に実務経験は不要で、誰でも挑戦できることから、多くの企業が新人教育の一環として2級取得を推奨しています。
1級は、職場の小集団におけるリーダーとして、自主保全活動の計画立案や実践指導ができるレベルです。チーム全体の保全活動を統括し、メンバーへの技術指導や改善活動の推進役として活躍することが期待されます。1級の受験には原則として4年以上の実務経験が必要とされており、現場のリーダー候補者が目指す資格として位置づけられています。
製造現場で自主保全士が担う5つの具体的な業務
製造現場において自主保全士は、設備の安定稼働を支える様々な業務を担当しています。その活動は日常的な設備管理から異常時の対応まで多岐にわたり、生産活動の基盤を支える重要な役割を果たしています。ここでは、自主保全士が実際に行う5つの主要業務について詳しく見ていきます。
設備の日常点検で異常の早期発見を実現
自主保全士の最も基本的かつ重要な業務が、設備の日常点検です。稼働前、稼働中、稼働後の各段階で、設備の状態を細かくチェックし、正常に動作しているかを確認します。
点検では、機械から発せられる音の変化、振動の大きさ、温度の上昇、油の色や量、部品の摩耗状態など、五感を使って設備の状態を観察します。経験を積んだ自主保全士は、わずかな音の違いや振動パターンの変化から、設備の異常を察知できるようになります。
点検結果は専用のチェックシートに記録し、データとして蓄積していきます。この記録は、設備の経年変化を把握し、適切なメンテナンス時期を判断する重要な資料となります。また、異常の兆候を早期に発見することで、大きなトラブルに発展する前に対処でき、計画外の設備停止を防ぐことができます。
CILT活動(清掃・点検・潤滑・増し締め)で故障を未然防止
CILT活動は、Clean(清掃)、Inspect(点検)、Lubricate(潤滑)、Tighten(増し締め)の頭文字を取った、設備保全の基本活動です。自主保全士は、この4つの活動を日々確実に実施することで、設備の劣化を防ぎ、故障を未然に防止します。
清掃では、設備に付着したホコリや切粉、油汚れを丁寧に取り除きます。汚れの蓄積は放熱不良や可動部の固着を引き起こし、設備の性能低下や故障の原因となるため、定期的な清掃は欠かせません。
潤滑作業では、指定された箇所に適切な種類と量の潤滑油やグリスを供給します。油切れは摩耗の促進や焼き付きを引き起こすため、潤滑状態の管理は設備寿命に直結します。
増し締めでは、振動によって緩みやすいボルトやナットを定期的に点検し、必要に応じて締め直します。部品の緩みは、位置ずれや破損の原因となり、重大事故につながる可能性もあるため、確実な締結管理が求められます。
消耗品交換や簡易修理により設備停止時間を短縮
自主保全士は、フィルターやパッキン、ベルトなどの消耗品の状態を日常的に監視し、劣化が進む前に計画的に交換します。消耗品の突発的な破損による設備停止を防ぐことで、生産計画への影響を最小限に抑えます。
また、簡単な不具合であれば、その場で修理や調整を行います。センサーの位置調整、配線の接続確認、簡単な部品の締め直しなど、専門技術者を呼ばなくても対処できる作業は自主保全士が即座に対応します。
ただし、自分の技術レベルを超える修理や、安全上のリスクがある作業については、無理をせず専門の保全部門に依頼する判断力も重要です。適切な判断により、問題の悪化を防ぎ、効率的な設備復旧を実現します。
異常発生時の初期対応で生産ロスを最小化
設備に異常が発生した際の初期対応は、被害の拡大防止と早期復旧の鍵となります。自主保全士は、異常を検知したら直ちに設備を安全に停止させ、周囲の安全を確保した上で、原因の特定に取り組みます。
異常の状況を正確に把握し、音、振動、温度、表示ランプの状態など、五感で得られる情報を詳細に記録します。簡単な原因であれば、リセット操作や詰まりの除去など、その場で対処して生産を再開します。
自力での復旧が困難な場合は、収集した情報を整理して上司や保全部門に報告します。現場の状況を正確に伝えることで、専門技術者による効率的な修理作業が可能となり、結果的にダウンタイムの短縮につながります。
保全記録の管理と改善提案で継続的な稼働率向上に貢献
自主保全士は、日々の点検結果や作業内容を記録し、設備ごとの傾向分析を行います。蓄積されたデータから、特定の部品の寿命パターンや、トラブルが発生しやすい条件などを把握し、予防保全の計画立案に活用します。
また、現場での経験を基に、設備の改良や作業手順の改善提案を積極的に行います。例えば、頻繁に故障する箇所の構造変更や、点検項目の見直し、作業効率を向上させる治具の導入など、実践的な改善アイデアを提案します。
これらの活動を通じて、PDCAサイクルを回し、継続的な改善を推進します。小さな改善の積み重ねが、設備の稼働率向上と品質安定に大きく貢献することになります。
自主保全士に求められる4つの必須能力とスキル
自主保全士として活躍するためには、特定の能力とスキルを身につける必要があります。JIPMでは、これらを4つの能力として体系化しており、それぞれが現場での実践活動に直結する重要な要素となっています。
異常発見能力:わずかな変化も見逃さない観察力
異常発見能力は、設備の正常状態を基準として、そこから逸脱した状態を的確に認識する力です。この能力の核心は、日常的に接している設備の「いつもと違う」という微細な変化に気づく鋭い観察力にあります。
優れた自主保全士は、モーターの回転音がわずかに高くなった、振動のリズムが不規則になった、潤滑油の色が濁ってきた、といった小さな変化も見逃しません。これらの兆候は、将来的な故障の前触れであることが多く、早期に発見できれば大きなトラブルを防げます。
この能力を養うためには、まず設備の正常状態を正確に把握し、その特徴を体で覚えることが重要です。日々の点検や清掃作業を通じて設備と向き合い、細部まで観察する習慣を身につけることで、異常を見抜く眼力が養われていきます。
処置・回復能力:迅速な応急処置で稼働を維持
処置・回復能力は、発見した異常に対して適切な対処を行い、設備を正常な状態に戻す実行力です。この能力には、技術的な知識とともに、状況を冷静に判断し、最適な対処方法を選択する判断力が含まれます。
軽微な不具合に対しては、工具を使った簡単な修理や調整を行い、速やかに生産を再開させます。一方で、自分の技術レベルを超える問題については、状況を正確に把握した上で、専門部署への連絡や応援要請を適切に行います。
この能力を高めるには、設備の構造や動作原理を理解し、基本的な保全技術を習得することが必要です。また、過去のトラブル事例を学習し、様々な状況に対応できる引き出しを増やしていくことも重要です。
条件設定能力:正常と異常を判断する基準づくり
条件設定能力は、設備管理における「正常」と「異常」の境界線を明確に定める能力です。振動値、温度、圧力などの数値的な管理基準を設定し、客観的な判断ができる仕組みを作ります。
例えば、ベアリングの温度が何度以上になったら要注意とするか、潤滑油の汚染度がどの程度になったら交換するか、といった具体的な基準値を設定します。これにより、経験や勘に頼らない、誰もが同じ判断ができる管理体制が構築されます。
基準値の設定には、設備メーカーの推奨値を参考にしながら、実際の使用環境や生産条件を考慮して最適な値を決定します。また、設定した基準が適切かどうかを定期的に検証し、必要に応じて見直しを行う柔軟性も求められます。
維持管理能力:ルールを守り継続的改善を推進
維持管理能力は、設定したルールや基準を確実に守り続けるとともに、それらを継続的に改善していく能力です。単にルールを守るだけでなく、現場の状況に応じて主体的に改善を進める姿勢が重要です。
日々の活動では、決められた点検項目を漏れなく実施し、記録を正確に残します。同時に、活動の結果を分析し、より効果的な方法がないか常に考え、改善提案を行います。
また、チーム全体の維持管理レベルを向上させるため、後輩への指導や情報共有にも積極的に取り組みます。自主保全の文化を職場に根付かせ、全員が主体的に設備管理に参加する環境づくりに貢献することも、この能力の重要な要素です。
保全エンジニアと自主保全士の役割分担と協働関係
製造現場の設備保全は、自主保全士と保全エンジニアが協力して成り立っています。両者はそれぞれ異なる専門性と責任範囲を持ちながら、互いに補完し合う関係にあります。効果的な設備管理を実現するためには、この役割分担と協働の仕組みを正しく理解することが重要です。
日常保全と専門保全で異なる責任範囲
自主保全士が担当する日常保全は、毎日の生産活動の中で行う基本的な保全活動です。清掃、点検、給油、増し締めといった作業を通じて、設備を常に良好な状態に維持します。また、簡単な消耗品の交換や軽微な不具合の修正など、生産を止めずに対処できる範囲の作業を担当します。
一方、保全エンジニアが担当する専門保全は、より高度な技術と専門知識を要する保全活動です。定期的な精密点検、振動解析や油分析などの診断技術を用いた予知保全、大規模な分解整備やオーバーホール、設備の改造や更新計画の立案などが含まれます。
この役割分担により、自主保全士が日常的な管理で設備の状態を維持し、保全エンジニアが専門的な視点から設備の信頼性を高めるという、効率的な保全体制が実現されます。重要なのは、両者が情報を共有し、連携して活動することです。
必要な知識・技能レベルの違いと相互補完
自主保全士には、担当設備の基本的な構造と機能、日常的な保全作業の手順、安全に関する知識などが求められます。実践的な技能として、工具の使い方や簡単な測定器の操作、異常の見分け方などを身につける必要があります。
保全エンジニアには、機械工学、電気・電子工学、制御工学などの専門的な工学知識が必要です。また、CADを使った図面作成、各種診断機器を用いた精密測定、故障解析と対策立案など、高度な技術力が求められます。
両者の知識・技能の違いは、相互補完的な関係を生み出します。自主保全士が現場で収集した詳細な情報は、保全エンジニアの故障解析や改善計画に活用されます。逆に、保全エンジニアの専門知識は、自主保全士の教育や技術指導に活かされ、現場の保全レベル向上に貢献します。
資格制度の違い:民間資格と国家資格の位置づけ
自主保全士は、JIPMが認定する民間資格であり、主に企業内での人材育成とスキル評価を目的としています。取得しやすさと実践性を重視した制度設計により、多くの製造オペレーターが挑戦できる資格となっています。
保全エンジニアの代表的な資格である機械保全技能士は、厚生労働省が所管する国家資格です。技能検定制度の一環として位置づけられ、公的に技能レベルを証明する資格として、業界全体で高い評価を受けています。
資格の位置づけは異なりますが、どちらも製造現場にとって重要な価値を持っています。自主保全士は現場の実践力を、機械保全技能士は専門的な技術力を証明するものとして、それぞれの立場で設備保全に貢献しています。多くの企業では、両資格を組み合わせたキャリアパスを設定し、段階的なスキルアップを支援しています。
製造現場の安定稼働を支える自主保全士の重要性
現代の製造業において、自主保全士の存在価値はますます高まっています。高度に自動化された生産ラインでは、一つの設備トラブルが全体の生産活動に大きな影響を与えるため、日常的な設備管理の重要性が増しています。自主保全士は、この課題に対する解決策として、製造現場の競争力強化に貢献しています。
実際の導入効果として、ある自動車メーカーでは自主保全士制度の導入により、設備起因の生産停止が半減したという報告があります。また、オペレーター一人ひとりの設備に対する意識が向上し、品質不良の早期発見や安全意識の向上といった副次的な効果も生まれています。
今後の製造業では、少子高齢化による熟練技術者の減少や、設備の高度化・複雑化への対応が課題となります。これらの課題に対して、自主保全士制度は現場オペレーターの能力向上を通じた解決策を提供します。
「自分の設備は自分で守る」という自主保全の理念は、単なる設備管理の手法を超えて、製造現場で働く人々の意識改革と成長を促進する仕組みとして機能しています。自主保全士として身につけた知識とスキルは、個人のキャリア形成だけでなく、日本の製造業全体の発展に貢献する重要な資産となっています。
手に職つくお仕事探しは求人サイト「e仕事エンジニア」がおすすめ!
手に職つくお仕事に興味がある人は求人サイト「e仕事エンジニア」がおすすめ!
例えば
- 大手メーカーで最先端の技術を身につけられる
- 資格取得をサポート
- 未経験でも安心の充実研修
など様々なメリットがあります。無料で利用できるのでぜひチェックしてみてくださいね。
e仕事エンジニアはこちらから↓↓↓
関連記事
求人カンタン検索
こだわりのメリットでカンタン検索。希望の条件をクリックして下さい。
都道府県で探す
業種で探す
こだわり条件で探す
- 待遇
- 働き方
- 募集条件
- 職場環境